川越で相続登記・不動産相続のご相談なら
川越相続の窓口
運営:司法書士法人 中山ゆり事務所
〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-22長栄川越ビル(旧八十二銀行川越ビル)4F
西武新宿線「本川越」徒歩2分東武東上線「川越市」徒歩8分「川越」駅徒歩10分 専用駐車場有
【高田馬場支店】 東京都新宿区高田馬場3-2-14 天翔高田馬場ビル209号室
第2.4土曜日9:00~17:00
相続放棄などの裁判所手続き
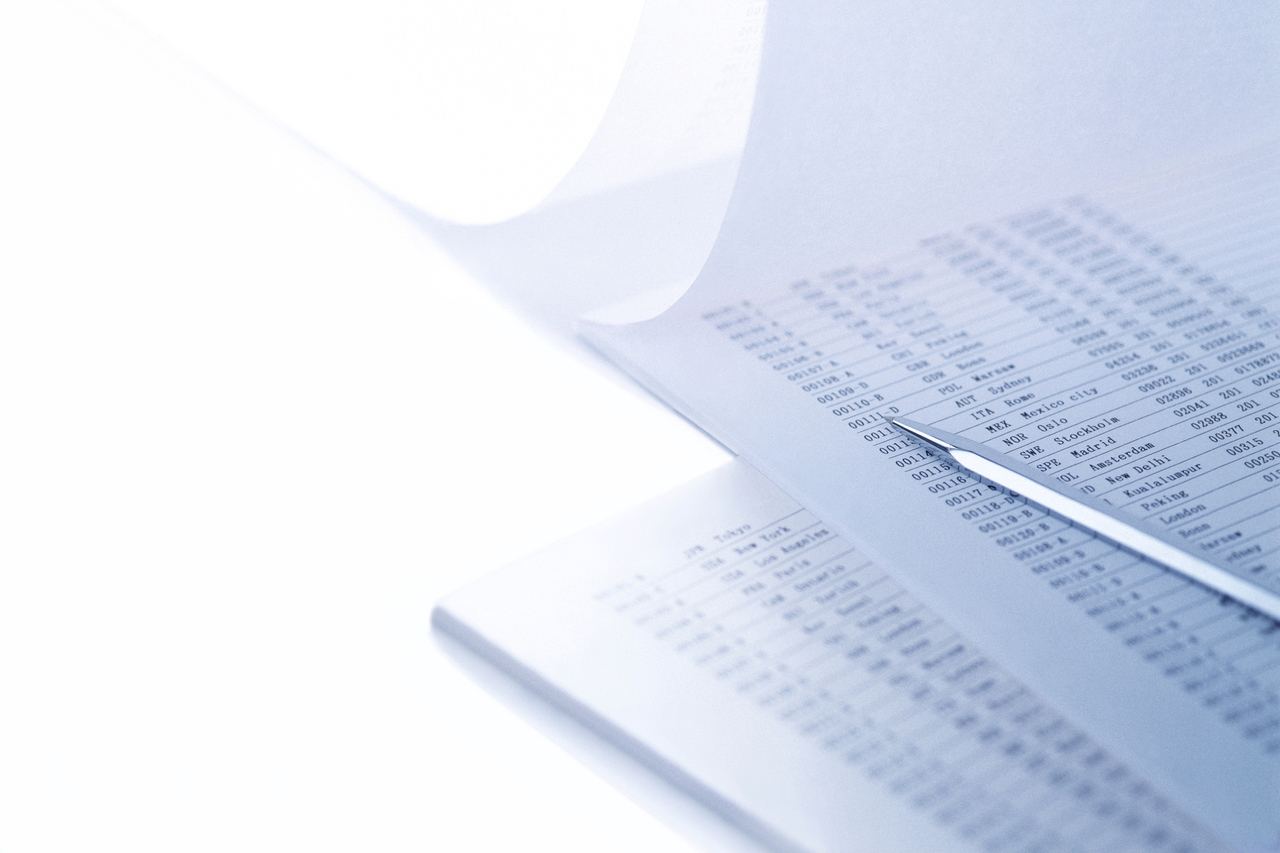
ある日、突然金融業者から身に覚えのない請求書が届いた・・・
宛名を見ると、全く交流の無かった叔父の名前の下に、「相続人○○様」と書いてあった。
とてもじゃないが支払うことはできないし、どうすればいいの?
そういったご相談をいただくことがございます。そんなときは相続放棄を検討されることをお勧めします。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、借金を支払う必要はなくなります。
仮にプラス財産があっても受け取ることはできなくなりますが、こういったケースではプラス財産は何もないかあっても少額の場合がほとんどです。
上記のケースでは、相続放棄は亡くなった叔父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
例)叔父の最後の住所地が、
川越市・所沢市→川越支部
飯能市・日高市・東松山市→飯能出張所
さいたま市→本庁
また、相続放棄には期限がありますので、お早目にご相談されることをお勧めします。
相続放棄をご依頼いただくメリット
戸籍謄本等必要書類の収集・申述書の作成を全て代行

上記の例では「叔父」と書きましたが、仮にこの例の場合、
・叔父の住民票除票または戸籍の附票
・叔父の出生~死亡までの戸籍謄本
・祖父祖母の死亡の記載のある戸籍謄本
・親(叔父の兄弟)の死亡の記載のある戸籍謄本
・ご依頼者様の戸籍謄本
が少なくとも必要になりますが、
必要書類一式はこちらで取得し、申述書の作成もこちらで行いますのでお客様にご負担はかかりません。
相続人全員でのご依頼も可能

上記のケースでは、ご依頼者様の兄弟姉妹も相続人となっています。そのため、兄弟姉妹全員一緒に相続放棄されることをお勧めします。
また、亡くなった親の債務を残った方の親と子が相続放棄すると、順位が繰り上がり、次は亡くなった親の両親、その次は兄弟姉妹が相続人となります。一人でも放棄しない相続人がいるとその人が借金を背負うことになってしましますので注意が必要です。
相続放棄には期限があります!
相続放棄は、「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければなりません。
但し、これを過ぎていても事情によっては相続放棄が認められるケースもありますのでご相談下さい。
相続放棄に関する料金表
| 相続放棄申述書作成(1名様あたり) | 33,000円(税込) |
|---|
代襲相続または数次相続の場合、代襲相続人(数字相続人)一人につき11,000円(税込)が加算されます。
きょうだい相続の場合、11,000円(税込)が加算されます。
死亡日から3か月以上経過している放棄者場合1名につき11,000円~を加算。
| 戸籍等取得費(実費) | ケースにより異なります (5,000円~15,000円くらい) |
|---|
※上記とは別に、家庭裁判所への印紙代(1人あたり800円)と予納郵券代(家庭裁判所により異なります・さいたま家庭裁判所川越支部は一人当たり470円)がかかります。
| 〔モデルケース①〕 全く交流の無かった叔父が亡くなり、知らない金融業者から叔父の債務を支払うよう、通知書が届いた。(父は先に死亡)金額も大きく、プラス財産はないので相続放棄したい。 | |
|---|---|
| 相続放棄申述書作成手数料 | 55,000円(税込) |
| 戸籍謄本等取得費・通信費 | 15,000円 |
| 印紙・予納郵券 | 1,270円 |
| 合 計 | 71,270円 |
| 〔モデルケース②〕 父が亡くなり相続人である長男・長女が相続放棄をする場合。(母は父より先に死亡) | |
|---|---|
| 相続放棄申述書作成手数料 | 66,000円(税込) |
| 戸籍謄本等取得費・通信費 | 5,000円 |
| 家庭裁判所への印紙代・予納郵券 | 2,540円 |
| 合 計(2名様分) | 73,540円 |
相続放棄申述の流れ
お問合せ

お電話(TEL:049-227-7772)、または、お問合せフォームより、
お問い合わせください。
ご相談内容を伺い、面談の日時を決定します。
事務所にお越しいただくことが困難な場合、出張相談も可能です。
必要書類書類の収集

資料があればお預かりし、戸籍謄本や住民票除票を集めて相続放棄申述書をこちらで作成します。
内容をご確認いただいた後、押印をいただき、当事務所から家庭裁判所に相続放棄申述の申立書を提出します。
家庭裁判所に申述 → 照会書の送付

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、後日家庭裁判所から
照会書(相続放棄が申述人の真意に基づきなされたか、内容に間違い
ないかといった確認の書類)が届きますので、記入して返送します。
記載方法についてはサポートさせていただきます。
相続放棄の完了 → 債権者への通知

家庭裁判所が照会書と申述書に齟齬がないことを確認し、相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
ただし、これはあくまで通知書であるため、必要に応じて家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
金融業者等から請求や督促があった場合、上記の通知書または証明書を相手に提出して下さい。



